ブログ
ブログ2023.09.25
解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ③

解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ③
大阪府大阪市中央区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ③】についてご紹介していきたいと思います。
~建物滅失証明書~
建物滅失証明書は、解体工事を施工した業者が作成する書類です。
建物取毀(とりこわし)証明書とも呼ばれています。
受け取ったら解体工事をした建物の所在地などの表示や所有者、解体工事の理由、解体工事をした日付と施工業者がきちんと記載されていることを確認しましょう。
インターネットなどで事前にテンプレートを基に証明書を作成して、解体業者に押印をして送り返してもらうという方法も有効です。
~解体業者証明書と印鑑証明書~
解体業者証明書と印鑑証明書は、解体業者から建物滅失証明書とセットで発行されます。
建物滅失証明書の工事人の証明をするための書類となります。建物滅失証明書の印鑑証明書と共に解体工事の完了後に受け取ります。
解体業者資格証明書は、全部事項証明書や代表者事項証明書、現在事項証明書や現在事項一部証明書などの名称の書類の発行がされる場合もあります。
建物滅失証明書の工事人欄の記載内容と同じことを確認しましょう。
~委任状~
建物所有者本人が建物滅失登記を行わない場合は、委任状が必要となります。
建物所有者が手続きを行う場合は不要ですが、代理人が行う場合には作成をしましょう。
土地家屋調査士に依頼するとセットで準備をしますが、もちろん費用に含まれます。個人で行う場合はネット上のテンプレートなどを参考にするとよいでしょう。
記載内容は登記の目的や原因、不動産の表示や指定した代理人の住所、氏名などです。原則として実印を使用して、建物所有者の印鑑証明書の添付をします。
~建物の登記簿謄本・図面など~
解体工事をした建物の登記簿や図面は、管轄の法務局で入手することができます。
建物の登記簿は、全部事項証明書の請求をします。図面は地図や土地所在図、地積測量図(筆界特定書)、建物図面及び各階平面図を一括で請求することが可能です。
登記簿は建物の所有者の氏名や住所、抵当権の設定などの確認をし、図面では建物の位置関係、地積測量図では土地の特定、各階平面図では形状の確認をしっかりしましょう。
~まとめ~
今回は【解体工事の後 建物滅失登記が必要なワケ③】をご紹介しました。
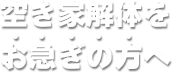
-
早急に対応いたしますので、
まずはご連絡ください。

 大阪・兵庫空き家解体No.1の実績
大阪・兵庫空き家解体No.1の実績

 営業時間 9時〜18時|年中無休
営業時間 9時〜18時|年中無休